目次
「会議の生産性が悪くて…」
という声は、
実に多くの場面で耳にします。
会議を生産的・効率的に実施するための要素は、
たくさんあるわけですが、
ひとつの要素は、「ファシリテーター」の効果性。
ファシリテーターが、
以下に上手に会議をコントロールするかによって、
会議の生産性は大きく変わります。
というわけで今回は、
そのファシリテーターの「コミュニケーション」について。
さらにその「コミュニケーションの中の」
「質問」についてポイントやコツをお伝えしていきます。
この記事の信頼性
私はPHP研究所の、
「認定ビジネスコーチ(上級)」
および
「認定チームコーチ」
です。
コーチングと会議の進め方については、
合わせて2年間に渡って、
みっちりと学びました。
また、規模や業種もさまざまな企業に対し、
実際に会議のファシリテーターを請け負ったり、
会議を生産的にやるための研修を実施したりしています。
こんな方にオススメ
- 会議の生産性を上げたいと考えている方
- 会議を取り仕切る立場の方
- 自社の会議の文化を変えたいとお考えの人事の方
この記事でわかること
なぜファシリテーターの質問の「質」が大事なのか
質問のやり方とポイント

たった3つの質問で会議を上手にコントロール【ファシリテーターのコミュニケーション術】
さっそく結論から行きます。
ファシリテーターが知っておくべき、
質問の種類はたったの3つです。
その1:クローズドクエスチョンとオープンドクエスチョン
最初に言っておくと、
基本的に使っていきたいのは、
「オープンドクエスチョン」です。
クローズドクエスチョン
「質問者」によって、
選択肢(回答)が決められている、
制限されている質問。
回答者の答え方は、
Yes/Noか、
与えられた選択肢の中から選ぶということになる。

メリット:答えるのが簡単で時間がかからない
デメリット:真実が見えづらい、質問者の意図に誘導される
オープンドクエスチョン
答えの選択肢がない。
なので、何かに縛られることなく、
相手は自由回答が可能。
5W3H。
(When,Where,Who,What,Why,How,Howmany,Howmuch)

回答者の答え方は、
(質問の趣旨や方向性に応じて)、
自分で答えを考え、
自分で言葉を選び、
自分の論理構成で答えることができる。
メリット:その人が考えているより真実に近いことがわかる
デメリット:答えを出すのに時間がかかることがある。
その2:掘り下げる質問と拡げる質問
掘り下げる質問
相手の話を具体的にする。
その意図は2つ。
- 発言者の考えを明確にするためのサポート
- 会議に参加する他のメンバーの正確な理解を促す
<質問例>
・「それってどういうこと?」
・「具体的には?」
・「もっと詳しく教えて」
など
まず、
人は発言しながら、
自分でも自分の考えや気持ちなどが、
よく理解できていないことがある。
その状況を、
自分自身でしっかりと把握するために、
この質問を用いる。
また、人が発言して、
それを受け取ったときの、
会議の参加メンバーの解釈は、
思うほどには一致していない。
わかったフリをする。
適当な理解でやり過ごす
認識の齟齬は、
後々の組織活動における、
思わぬロスとなる。
会議の最中に、
認識をしっかりと合わせることが大切となる。
拡げる質問
これは、
最初に出てきた状況やアイデアを、
横展開していくための質問。
質問例は、
たったひとつでOK。
<質問例>
「他には?」
↓いろいろ使える
「他には何をしてきた?」
「他に気になっていることは?」
「現状として他に話しておきたいことは?」
「他にうまくいっていることは?」
「他にどんなことができたかな」
「他に協力してくれた人は?」
「他にどんなアイデアがあったの?」
「他にはどんな強みがある?」
「他に得意なことはどんなことがあるかな?」
「他に楽しいことは?」
「他にやりがいを感じる場面は?」
「他に大切にしている価値観は?」
…
とまあ、無限に出てくる
上記は「過去」や「現在」
つまり、すでに起きていることに関する質問。
「他にやってみたいことは?」
「他に目標としていることは?」
「他にどんなアイデアがある?」
「他に試してみたいことは?」
「他に大事にしていきたい価値観は?」
「他に身につける必要のある能力は?」
「他に組織に対して貢献できることは?」
…
とまあ、未来に関しても汎用性が高い。
ポイント
よく、
「他には?」
を続けると、
「しつこい」って思われるのでは?
詰めているようで気が引けるのですが…。
などと質問をいただくのですが、
基本的に人は、
質問をされることはストレスなんです。
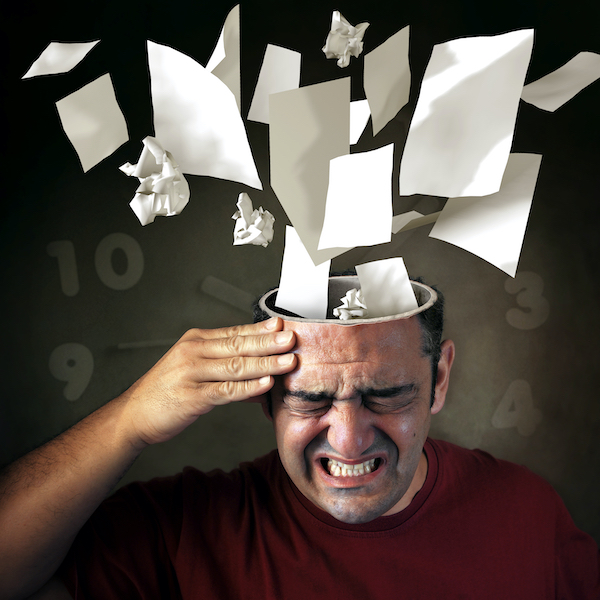
考えないといけないですからね。
そして、
考えた末に出した答えが、
「否定されるかも」
という不安や怖れも持っています。
なので、
訊き手の姿勢が大切です。
「答え焦ってないからゆっくり考えて」
とか
「すべての答えはOK」
というスタンスをベースとして持っており、
それが相手に対して、
態度や振る舞いも含めて、
伝わっていく必要があります。
その3:過去質問と未来質問
これは単純なのでさらりと…。
過去質問:過去のことを訊く
未来質問:未来のことを訊く
ファシリテーターは、
今この会議の場は、
過去のことを扱う時間なのか、
未来のことを扱うべき時間なのか、
コントロールする必要があります。
過去に囚われて終了する会議はありません。
組織として、
過去の情報は、成功も失敗もすべて、
新しい未来を作っていくための情報です。
会議は必ず未来志向です。
過去に囚われて未来をつくるための時間が奪われるのは、
本末転倒です。
過去に関する情報が十分に出たなと思ったら、
しっかりと全体の意識を未来に向けていきましょう。

欠陥会議で起こっている2つのこと
メンバーは自分の意見や考えがわかっていない
議論されている内容があるわけですが、
その内容に関する十分な自分の理解がなかったり、
知識や経験がなかったり、
あるいは、
知識や経験があったとしても、
十分に考えていなかったりすると、
どうしてもその人の思考は曖昧になります。
なんとなくの考えを発信して、
まわりは理解した気になる。
他のメンバーは理解しているようで理解していない
コミュニケーションは、
誤解の嵐です。
発信された内容は、
その人の語彙で、
その人の言葉の意味で発信されています。
言葉の意味は、
「辞書の意味」はありますが…、
それぞれ違います。
例えば「自由」という言葉。
人の解釈はやっぱりいろいろ。
「好き勝手やること」
「自分で選ぶことができるということ」
瀬戸内寂聴さんは、
J-waveの「今日という日に力を与えるお言葉」で
「こだわりを捨てること」
って言っていました。
私が以前出会った研修の受講生は、
「自由というのは、全部決まっていることだ」
って言っていました。
まったく違う解釈ですよね。
「成功」のイメージ
「頑張る」のイメージ
「必死に」のイメージ
「休む」のイメージ
一致しているんだとしたら、
本当にたまたまです。
「まあいいか」で真実が見えない
安易なクローズド・クエスチョンをすると、
「完全に合っていないけど、
間違えてもいないからまあいいか」
と、解釈が十分に合わない状態で、
先に進んでしまいます。
まあ正確には、
理解がずれるわけですね。
これは危ないんです。
クローズド・クエスチョンというのは、
質問する人が、
自分の推測が前提となって、
投げかけられるわけですね。
(質問者)
「睡眠が足りないからやる気がでないということじゃないかな?」
(回答者)
「まあそうですね…」
それも一つの要因だけど、
他にもより重要な要因があるかもしれない。
でもそのことは、
表現されないわけです。
正しい理解を妨げる心理的要因
以下のような心理状態が、
メンバー間の質問のやり取りを妨げる。
まあつまり、
メンバーは以下のような理由で、
質問しないということです。
- 馬鹿だと思われたくない
- 失敗したくない
- 恥をかきたくない
- 早く終わらせたい
- 興味関心がない
だから、
ファシリテーターがメンバーに変わって、
質問を投げていくわけですね。
ファシリテーターがわかっていても、
「他のメンバーのために」
質問を投げます。
ファシリテーターの質問が大切な理由
ファシリテーターの質問はメンバーの思考を明確にする
ファシリテーターは、
考え尽くしていない、メンバーの思考を、
さらに明確にすることができます。
まあ平たく言えば、
「ちゃんと考えさせる」ということ。
まあ、会議の中でコレをやりすぎると、
他の人の時間を奪うことにもなっちゃったりするので、
状況をみながら適度にということになりますが。
でもそこで考えを促して、
アイデアをちゃんと出してもらわないと、
会議が進まないような局面では、
やはり「掘り下げて」「拡げて」、
明確にする必要があります。
ファシリテーターの質問は全体の理解を共通化する
ここでもやはり、
「掘り下げて」「拡げて」行くことで、
各自が勝手に解釈していたものが、
共通化することになっていきます。
「勘違い」は、
本当にたくさんありますから。
人は、自分の色眼鏡で、
見たいように見るし、
聞きたいように聞いています。
メンバー全員の解釈が、
必要最小限合うように、
質問を繰り返していきましょう。
↑ここで、
「必要最低限ってどのくらい?」
って質問が出てきたら、
「掘り下げる質問」はバッチリです。
必要最低限というのは、
残念ながら定義できません。
ファシリテーターをやりながら、
感覚的に掴んていくものと思いますが、
どれだけ経験を積んだとしても、
正解と言えるものには出会わないでしょう。
きょうのまとめ
というわけで、
今日お伝えしたい重要なことは3つ。
- オープンクエスチョン使いましょう
- 会議参加者の話を掘り下げて拡げて、
その真意や具体的なところを、
全体で共有できるようにしましょう。 - 未来を創造するための会議リードを、
心がけましょう
ファシリテーターの采配によって、
会議の生産性や効率は、
まったく変わってきます。
「会議に無駄が多い」
というのは実に多くの人が感じていること。
ちょっとした仕掛けの変化でも、
劇的に改善されることもあります。

是非勇気を持って、
メンバーを巻き込みながら、
会議の変革に取り組んでいきましょう。










